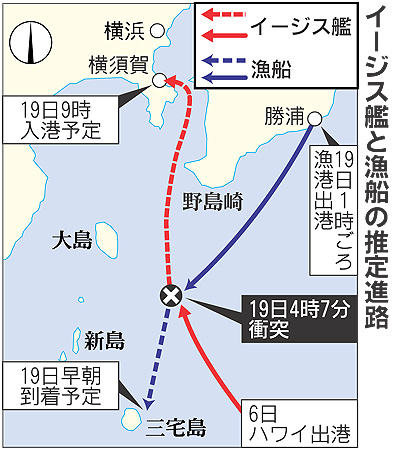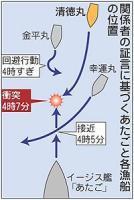私は、これまでのサッカーの国際試合で、
こんな酷いジャッジをする主審を見たことはありません。
こんな酷いラフプレーをする選手を見たことはありません。
そんな無法地帯のピッチで冷静にプレーし見事に完封して勝利
を勝ち取った日本の選手たちに、心より敬意を表したいと思います。
男子サッカー東アジア選手の二日目の2試合が、昨日20日、重慶で行なわれ、第一試合 日本対中国は1:0で日本が勝利し、第二試合 韓国対北朝鮮は1:1で引き分けました。この結果、韓国と日本が勝点4、得失点差+1で並びましたが、得点で2多い韓国が首位をキープして日本は2位につけ、3位 北朝鮮、4位中国の順となりました。この結果、3位の北朝鮮までに優勝の可能性が残ることになりました。
23日の3日目の第一試合 日本対韓国戦でいずれか勝った方が優勝、もし引き分けた場合、北朝鮮が中国に1点差で勝利すれば得失点差で+1で韓国、日本、北朝鮮が並びますが、得点で韓国が日本より2多いため日本の優勝は無くなり、韓国と北朝鮮いずれか得点の多い方が優勝することになります。北朝鮮が中国に1:0で勝った場合は韓国の優勝、2点以上得点して勝った場合は、日本対韓国戦次第ということになりますが韓国が圧倒的に有利であることに変わりありません。
この日の、日本対中国戦は、冒頭に述べておりますように、国際サッカー史上に汚点を残す醜い試合になってしまいました。それでも、主審の理不尽で理解に苦しむアンフェアな判定と中国人選手の危険極まりないラフプレーに耐えて冷静に試合を進めて勝利しました日本選手たちに拍手を送りたいと思います。この中国人選手のラフプレーで怪我をしたためにW杯で苦杯をなめた苦い経験を持つフランスでは、ジダンなど多くの元フランス代表たちは、「今後、中国と対戦したくない」と語っております。特に、下の画像の、中国人選手が鈴木選手の首を締め付けているシーンと、その下の画像の安田選手が相手DFに脇腹に膝蹴りを受けているシーンはラフプレーを象徴するものでした。


本来なら、このようなプレーは選手生命を脅かす危険性が有ることから、レッドカードの一発退場ですが、北朝鮮人主審の オ・タエソンはイエローカードしか出さず、警告もしておりませんでした。そのため、中国人選手たちはイエローで済むと高を食って、その後もやりたい放題にラフプレーを続けました。本来、審判は試合をうまくコントロールする役を担わなければならないのに、この北朝鮮人主審は逆に火に油を注いでラフプレーを助長しゲーム負傷者まで出す結果を招いてしまいました。日本選手団の大仁邦弥団長(日本協会副会長)は、この点を重く見て大会を主催する東アジアサッカー連盟に対し、再発防止を求める申し入れ書を提出しました。
このラフプレーには中国国内でも批判の声が上がっており、地元の中国のスポーツ紙「体壇週報」は、「中国チームは自らに最も野蛮なチームというレッテルを張った」とした上で「中国チームは技術や戦術レベルの向上に全力を傾注してこなかった」と指摘するとともに、戦績にこだわりすぎる中国サッカー協会幹部が選手をあおったとの見方を示し、中国選手が日本選手の首をつかんだことを挙げ「いかにバランスが崩れた心理状態だったかが分かる」とした上で「すべての選手が興奮していては、試合に勝てるわけがない」と批判しております。
前半、中国はボールを奪っては素早く前線につなぎ、サイド攻撃でチャンスを作り続ける一方、日本は、高いポジションで起用された安田がピッチを駆け回って攻守に貢献し、前半17分、左サイドの駒野のクロスを起点に、山瀬のゴールで日本が先制点を挙げ、GK楢崎を中心とした守備陣が体を張って中国の攻撃を防ぎ切り、1−0とリードして前半を終えました。 後半は一転して日本がペースを握ったもの決定機で安田が相手GKにファウルされて負傷交代してから中国にラフプレーが目立つようになり、日本選手が何度もピッチに倒れ込む場面が繰り返されたが、それでも日本は冷静に試合をコントローして相手に決定機を作らせず、結局1−0の完封勝利を収めました。
尚、注目された中国人サポーターの観戦態度は、ピッチの選手たちのラフプレーとは対照的に冷静でした。負けた瞬間にはペットボトルが投げ入れられ、日章旗が焼かれ、帰りの日本選手たちのバスを取り囲むなどの騒動は有ったものの、。君が代演奏でもブーイングも出ず、試合中は予想された反日行動は殆ど無かったと報道されております。この点、改めて中国人サポーターに敬意を表したいと思います。そのような態度で北京五輪に臨んで欲しいものです。